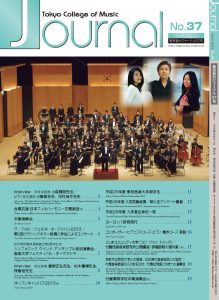
東京音大ジャーナル37号に小森輝彦のインタビューが
掲載されています。是非ご覧下さい!
詳しくはこちらから
ライマン氏のインタビュー記事
ショット・ミュージックのホームページに、昨年11月のオペラ公演「リア」の作曲者であるアリベルト・ライマン氏のインタビューが掲載されました。
インタヴュー:アリベルト・ライマン オペラ《リア》日本初演を終えて
小森の仕事ぶりや、「宮廷歌手」についても話しておられます。是非ご覧下さい。
音楽現代、音楽の友に記事が掲載されます
2月15日発売 月刊「音楽現代」3月号、および3月発売の月刊「音楽の友」4月号に、僕の記事が掲載されます。
3月21日の宮廷歌手叙任記念コンサートに関するインタビュー記事です。是非ご覧下さい。
コンサートの情報はこちら
二期会公演「ホフマン物語」インタビュー
二期会マクベスの出演者メッセージ
二期会21のブログに紹介されました
二期会21のブログ「オペラの散歩道」に小森の記事が紹介されました。
二期会『マクベス』掲載情報!『ぶらあぼ』でタイトルロール小森輝彦インタビュー
東テューリンゲン新聞2012年6月23日の記事
 東テューリンゲン新聞(ネット版)
東テューリンゲン新聞(ネット版)
「素晴らしい時を過ごしました」
宮廷歌手小森輝彦氏とのインタビュー。この日本人は12年の長きにわたってゲラに住み、ゲラでの仕事に従事した。今、彼は家族とともに彼の故郷へ帰ります。
OTZ:17年もドイツに住み、そのうちの12年をゲラで過ごされました。そして今、なぜ日本に戻られるのですか?
小森:私は歌を始めたときに、ドイツの劇場の専属歌手として働きたいという目標を持っていました。この目標は幸せなことに現実となりました。しかし私は最初から、永久にドイツに留まるつもりはなかったのです。
このドイツでの期間は、私にとって言わば「修業時代」のようなものです。もちろんプロとして舞台に立ちながらですが、私は多くのことをここで学びました。劇場での生活は、私が夢描いていたとおりのもので、私はとても幸せでした。そして今、次のステップに進まなくてはなりません。
OTZ:その次のステップとは?
小森:教鞭を執ることが一つの新しい役割です。私がここで得た経験を若い人たちに引き継ぎたい。声楽技術だけでなく、芸術と文化という視点から我々の仕事を捉えることも。
舞台人としても、今まで私は、ただ歌う事にだけ集中していれば良かったわけですが、これからはただ上手く歌うだけでは不十分です。一つのプロジェクトを包括的に俯瞰した上で公演全体に寄与する必要があります。
OTZ:長い間、異文化であるドイツの日常、ドイツのメンタリティーの中で暮らしてこられました。ドイツ生活を総括するとどうなりますか?
小森:ドイツの文化は以前から私の憧れでした。でも、日本で輸入品としてのドイツ文化を見聞きするのと、ドイツ文化が生まれた場所で実際に体験するのでは大きな違いがあります。この12年で東テューリンゲンは私の第二の故郷になりました。
この年月の中で、私は多くの友人や知人を得ることが出来ました。この土地で「お客さん」としてではなく、友として受け入れられること、これは本当に素晴らしいことでした。それに息子の健登にとってはドイツが故郷のようなものです。生まれは東京ですが、ほとんどの時間をここで過ごしましたから。
OTZ:12年間アルテンブルク・ゲラ市立歌劇場で歌われました。どんなシーンが想い出に残っていますか?
小森:ワーグナーの「さまよえるオランダ人」「ローエングリン」「タンホイザー」などをドイツで歌えたことは、私にとって大きな意義がありました。同様にプッチーニの「トスカ」や、ニーチェのオペラ「コジマ」での素晴らしい体験も忘れられません。
「コジマ」の作曲者であるジークフリート・マットゥス氏は私を以前から知っていたので、作曲の際にも私の声をイメージしてくれていました。私は哲学者のフリードリヒ・ニーチェを演じました。ニーチェが晩年、狂気の中で裸で彼の書斎で踊ったというエピソードから、オペラのクライマックスに取り入れられた「デュオニソスの踊り」は、踊りによる身体表現という意味で私にとって新たな挑戦でした。
OTZ:あなたは何人ものオペラ監督の下で歌われましたが、彼らはあなたの仕事の中で、どんな影響を与えましたか?
小森:私の最初のオペラ監督、シュテファン・ブリューアー教授は私の最初のメンター(経験に富んだ助言者)と言えます。とはいえアーティストとして常に意見が一致していたというわけではなく、コンセンサスにたどり着くために格闘してきました。この時期に私は、作品に没入すると言うことを学びました。役柄を「いのち」で満たすのです。ブリューアー教授の演出では、激しいアクションが求められました。
それに対して、私の二人目のオペラ監督でインテンダント(総裁)でもあったオルダーグ教授は、全てを凝縮する事を求めました。豪華な衣装に包まれた典型的で大時代的なオペラ歌手の演技は望まれていないわけです。
しかしこういう静的な表現はむしろ日本人が得意とするところです。日本を代表するオペラ歌手である私の師の一人が言っていたことを私は忘れられません。「もし私が歌唱によってのみ演劇性をも表現できたら、それが最高だ」と。少なさの中に豊かさがあるのです。音楽の中の演劇性を見出す事は、日本人としての私のモットーでもあります。そういう経緯を経て今、私は表現者として自分の仕事ぶりに確かな手応えを得られています。オルダーグ氏の指導によって表現者としてこの段階に到達できたことは、私にとって本当に幸福なことです。
OTZ:ゲラとアルテンブルクの聴衆を、あなたはどんな風に記憶にとどめておくのでしょうか?
小森:この劇場のお客様は、私を心から受け容れ、私を歌い手として更に育ててくれた聴衆です。この劇場の聴衆の皆さんから僕は本当に多くを学びましたし、共に育ってきたとさえ言えます。彼らは私の一部であり続けるでしょう。
それを助けてくれたのは、このアルテンブルクとゲラの劇場の理想的な「サイズ」です。聴衆が演じ手を間近に感じる事が出来て、演じ手のの涙や汗を見られる距離で、音が空気を振るわせる様を体験できる劇場なのです。ここでは巨大な劇場よりずっと多くのものが客席に届きます。
OTZ:オルダーグ総裁によってあなたは2011年4月に宮廷歌手の称号を贈られました。あなたにとって「騎士叙任式」のような事件でしたか?
小森:宮廷歌手の称号というのは私にとって、夢見ていた事さえ口に出すことも憚られる様なものでしたから。アルテンブルク市立歌劇場140周年記念のガラコンサートでこの称号を授与された時は本当に青天の霹靂でした。
数人の同僚が劇場の名誉会員の称号を授与されているのを見て、私は少し怪訝に思っていました。もし私も名誉会員に指名されるのであれば、年齢から言って若い私が最初に舞台に呼ばれるはずだったからです。袖に呼び出されたときは何が行われるのか知らされておらず、袖での待ち時間の間、お客様の前でどういう挨拶をするべきなのかと頭を巡らしていたのですが、そのことを告げられたときは本当に言葉が出てきませんでした。
OTZ:宮廷歌手として、あなたは最初でまた唯一の日本人と言うことですね・・・。
小森:はい。それをとても誇りに思っています。もちろんこれによって、私の責任はずっと重くなりました。私はより努力を続け、ソリストとしてより輝く義務を課せられたのです。
OTZ:ドイツの専属歌手から、日本でのフリーランスの歌手に。この変化に対応するのは難しいでしょうか?
小森:留学以前から日本でオペラ歌手として歌ってきましたし、この劇場での契約の間にも頻繁に日本に客演していました。私の故郷での仕事の様子は良くわかっていますから対応は難しくないと思いますよ。
この12年間は、毎日14時に発表になる稽古予定をみて翌日の稽古予定を知るという毎日でした。この日常的ルーチンがなくなることは寂しく感じるかも知れません。これからはもっと先の予定を厳密に立てて行かねばなりません。
専属契約では基本的に劇場を離れるのが難しく、日本からのオファーの三分の二くらいは断らざるを得ませんでしたが、これからは自由が大きくなります。。私は数年前から日本の私立音楽大学の客員准教授として教えていますが、これからもそうして教鞭を執るかたわら、オファーを受けて歌う仕事にも集中する必要があります。今まで日本で歌い続けられたのは、アルテンブルク・ゲラ市立歌劇場が専属契約の拘束がある中で最大限に好意的に日本への客演を許してくれたからです。これには私はとても感謝しています。
OTZ:どんな舞台の予定がありますか?
小森:11月には演奏会形式での「さまよえるオランダ人」でタイトルロールを歌います。そのあとはR.シュトラウスのオーケストラ歌曲の演奏会やベートーベンの第九交響曲のソロをつとめます。2013年の1月にはワーグナーの「タンホイザー」、5月には「マクベス」のタイトルロール、そのあとに2つのオペラが続きます。(主催者側で公演情報未発表のため詳報は追ってお伝えします:訳注)そのあとは震災の被災地である仙台での日本オペラでも主役を歌う事になっており、これは当地の歴史にちなんだ作品です。
OTZ:あなたが懐かしがるであろう「典型的ドイツ」のものとはなんでしょう?
小森:はい、時間と安らぎでしょうか。東京の生活は慌ただしいですから。私たちにはゲラ近郊のニーブラと言うところで、大きな庭と草原を持つ友人がいます。そこで私たちは大いにリラックスして、エスプレッソと共に安らぎの時間を満喫することが出来ます。これは日本人にとって難しい事なのですが、私たちはそういう機会を得て、また大変それを好ましく思っています。私はこういう安らぎの時を東京の忙しさの中でも失わないようにしたいのです。
特に息子の健登にとってはこの生活リズムは理想的でした。ほとんど毎週末と学校が休みの時にはこのニーブラの友人を訪ねています。息子はその友人が手作りのバンガローを新築したとき一緒に手伝ったり、そこで木を削って工作にいそしみました。この友人は息子にとって「ゲラでのおじいさん」みたいなものです。日本に戻ったら息子はとても寂しく思うでしょうね。
OTZ:ドイツ料理との別れは悲しいですか?
小森:ドイツのハムとソーセージが食べられなくなるのは悲しいですね。息子の大好物はテューリンゲンの焼きソーセージですし。日本に住むドイツ人は、ドイツ風のハムとソーセージが入手できずに苦労しているようです。でも私はインターネットで、東京でゲラでよく飲まれているケストリッツの黒ビールを扱っている店を見つけてありますよ。
OTZ:あなたの息子の健登くんはゲラではシュタイナー学校に通っています。東京ではどうなりますか?
小森:はい。東京にもシュタイナー学校があります。2010年の夏に帰国した際に、健登は三週間の間、この東京のシュタイナー学校に体験入学をすることが出来ました。川の流れなど自然が近くにあり、校庭には自分たちで作った釜があり、素晴らしい環境です。今ではその時の体験入学をきっかけにして、ゲラと東京のシュタイナー学校の間で文通が始まっています。私の家内がその手紙を訳して間を取り持っています。
OTZ:もう東京に家は見つけたのですか?
小森:まだなのです。9月にはマーラーのオーケストラ歌曲の演奏会で東京に戻りますので、その時に探すつもりです。緑が近くにある環境・・・ゲラでの家のように・・・に家が見つかると良いのですが。
OTZ:ドイツでいまだに馴染めないという事柄がありますか?
小森:頭で理解は出来ても受け容れにくいことと言うのはありましたね。メンタリティーの違いによるものでしょう。例えば買い物をするとき、最初の印象では、ドイツの店員さんは日本の店員さんの様に丁寧とは言えません。
でも、あとで気付いたのですが、日本の店員さんの丁寧さはマニュアルによる丁寧さで、ストレートな真心からではないことが多い。今では、ストレートでも正直なドイツの店員さんの姿勢を好ましく思います。
OTZ:どんなものをドイツから想い出の品としてトランクに詰める予定ですか?
小森:ツォイレンローダの陶芸家による食器のセットが気に入っています。数週間前のゲラの陶芸市で、いくつか買い足しました。カーラの陶器も持って帰りたいですね。息子の木の勉強机は大変気に入っていて、是非持って帰りたい。私の同僚のギュンター・マクルヴァルト氏が、彼のオペラの楽譜をたくさんプレゼントしてくれましたから、これは絶対に持って帰ります。残念ながら食品は持って行けませんが、そうでなければテューリンゲン風焼きソーセージとドイツのビールを持って行きたいところです。そしてドイツのパン。日本では、また自分でパンを焼くことになるでしょう。
OTZ:東テューリンゲンの我々は、あなたのドイツへの客演を期待できますか?
小森:もうフライトを10月31日に予約してあります。でもドイツにまた演奏のために必ず戻ってきます。ゲラの劇場後援会は、私の日本での演奏会を聴くために東京への旅行を企画してくれているようです。
インタビュアー:クリスティーネ・クナイゼル
宮廷歌手、称号授与関連の記事
宮廷歌手(Kammersänger)の称号授与に関連した新聞記事の一部です。全て翻訳してあります。
また、報告のエッセイはこちらです。
チャリティーコンサートの詳細記事
ドイツ連邦庭園博覧会 DVDのインタビュー
2006年4月から9月にかけて行われた、BUGA(Bundes Gartenschau・・・ドイツ連邦庭園博覧会)の様子を収めたDVDのなかで、BUGAに合わせて大規模な改築が行われた劇場の様子、改築後の再オープニングの記念公演となったオペラ「コジマ」に主演した小森のインタビューが収められています。


