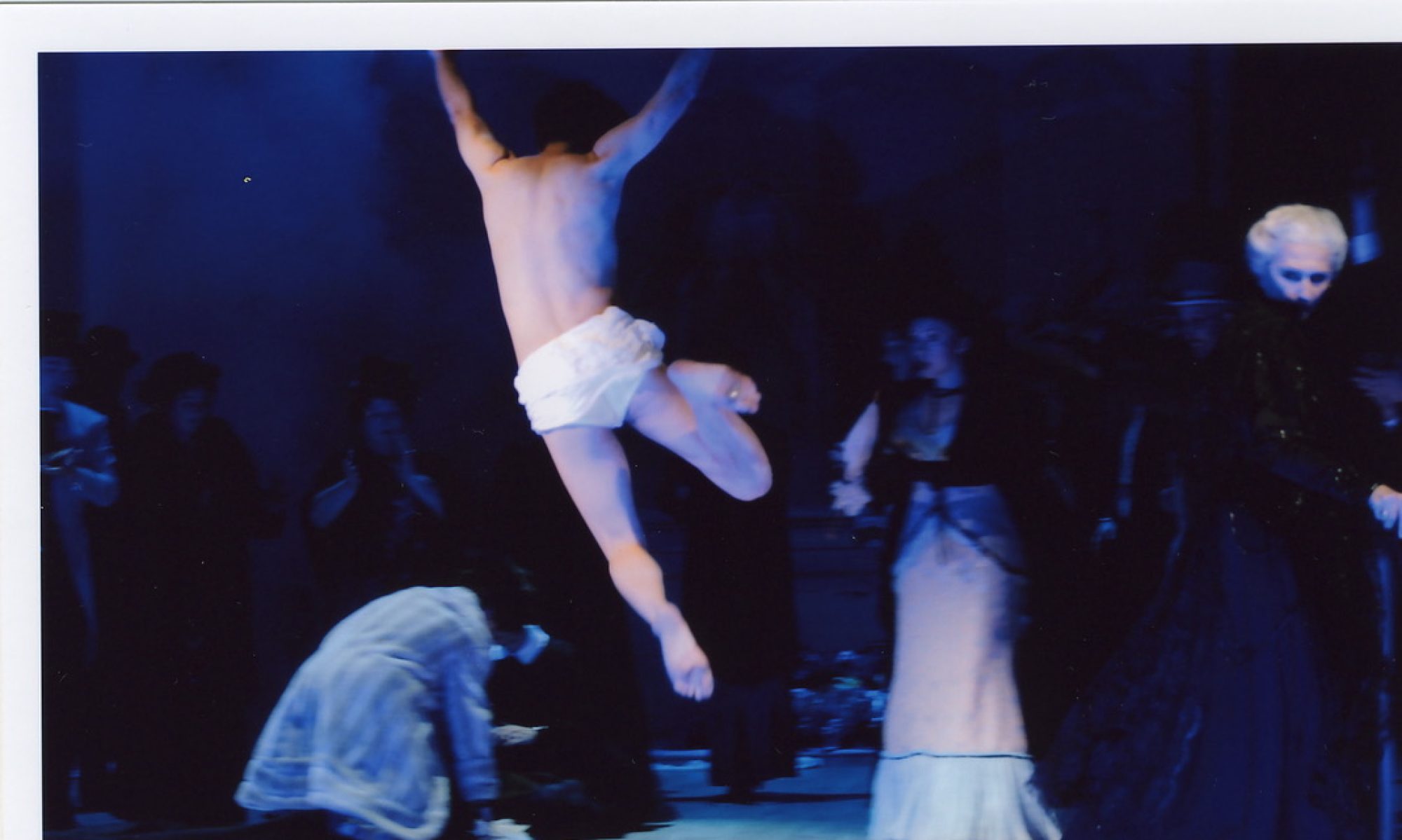今日は第九を歌ってきました。夏に第九というのは珍しいという感じがしなくもないですが、ミューザ川崎というホールの、夏のフェスティヴァルだそうで、祝祭的な意味がある場合は常に第九というのはあうわけで、そういう意味で良かったと思います。
前半はマエストロの小林研一郎さんのトークで、休憩後に第九、というプログラムでした。ここで小林さんはご自身の音楽との出会い、第九交響曲との出会いなどをお話しされたのですが、楽屋のモニターでこれを聞いていた僕はすっかり感動してしまいました。小林さんの入魂の指揮の源泉はここにあるのだ!と思いました。
小林さんの素晴らしいのは、第九交響曲を隅々まで完全に把握していらっしゃることはもちろんですが、常に一緒に歌っていらっしゃるんですね。合唱やソロのパートだけじゃないですよ、オーケストラのパートもずっと一緒に歌っているんです。隙というものは全くないし、心がこもっていないフレーズというのも一つもない。
今回はソリストは3楽章からホールに入ったのですが、僕は個人的には1楽章からホールに入って聴いていたかったです。
4日の芸術劇場大ホールでの練習で、小林さんの方から僕のソロパートについて、色々ご指摘がありました。ソロの始まりの部分、2フレーズ目のnicht diese Toene(こんな音ではない)のところを、きれいに歌うのでなく、言ってみればネガティブな心情を露わにして、歌うよりはしゃべって欲しいというご希望で、僕にしてみれば、歌わずにしゃべっちゃうのは得意なので、やりすぎそうな予感もあったので、いちおう「でも・・・音程はなくならない方が良いですかね?」とお聞きしたら、「いやぁ・・やっぱり音程はあった方が良いなぁ」というお答えで、合唱の皆さんの爆笑を誘ってしまいました。

有名なFreude schoener Goetterfunkenのところでは、小林さんがずっと指導していらっしゃると思われる合唱団、武蔵野合唱団の皆さんが、ずっと小林さんのイメージ通りのフレージングを練習していらしたと言うことでしょう。僕にイメージを伝えるために合唱団の皆さんがそのフレーズをどう歌っているかを一度僕のためだけに演奏して聞かせて下さいました。それではっきりと小林さんのイメージがわかりました。
そのイメージに向かって、GP、本番と、少しずつそこに歩み寄ろうと努力しました。本番では僕のソロが終わったところで僕に向かって指で「OK」サインを出して下さって、ほっとしました。
今回のソリストは、ソプラノの増田のり子さんをのぞいて、3人が「フィレンツェの悲劇」「ジャンニ・スキッキ」プロダクションの参加者でした。メゾの菅有美子さんはA組のビアンカ役、テノールの大間知覚さんはA組のリヌッチョでした。
大間知さんとは以前から仲良くさせていただいているんですけど、仕事で一番濃く共同作業が出来たのはコレギウム・ムジクム公演のカルメンでした。僕はあの舞台で肩の関節を壊したのだ・・・ははは。
この時に、大間知さんという歌手が、いかに全身全霊をかけて一つの舞台をおやりになるかという事を肌で感じているので、今回の「ジャンニ・スキッキ」でも、大間知さんのリヌッチョを見たときに、感動してしまって、この感動は100%が「ジャンニ・スキッキ」との関係とはいえないか?どうなんだ?なんて自問しながら、でも引き続き感動しながら見ていました。初日の本番が終わってから会いに行って、僕の感動は伝えたんだけど、その時も大間知さんは「明日頑張ってね」なんて言わない。「頑張ろうね!」という。違う組でも。うーむ。うなります、僕。
今回もご一緒できて嬉しかったです。本当に男らしいテノールですよね。男が惚れる男だ。