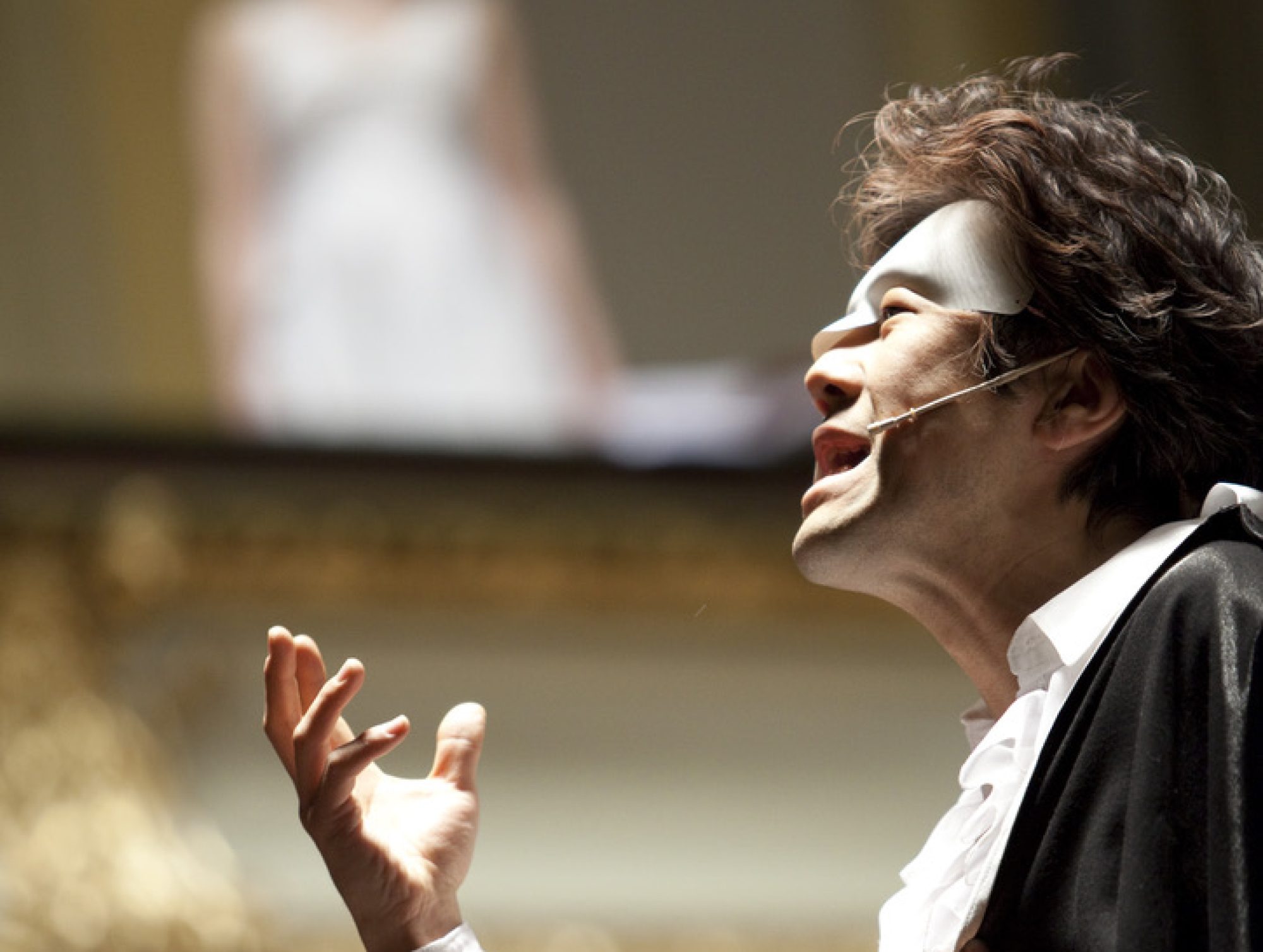ドイツはホメオパシー発祥の地なので、ホメオパシーを主な医療手段としている僕らには大変ありがたい状況であります。

とにかくレメディーの入手が容易であると言うこと。どの薬局でも注文すれば数時間後には大体のレメディーが手に入る。
それは良いんだけど、不便を感じる点もあって、その一つは、レメディーの名前が言語によってけっこう違ったりすることですね・・・。まぁ些細なことかもしれないけど。これは日本語だけの中でもけっこう問題あるなぁと思うときがある。英語から訳しているケースが多くて・・・日本はイギリスのプラクティカル・ホメオパシーが主流のようなのでそれも一因でしょうけど・・・レメディーの名前が、この英語の発音をどうカタカナに置き換えるかで、ずいぶん違っちゃうんですよね。
Pulsatilla,ポースティーラ、プルザティッラ。Nat.mur.ネイチュ・ミュア、ナト・ムール。Aconite, Aconitum,アコナイト、アコニトゥム、アコニット。もう分けわからなくなっちゃう。
さらにですね、同じレメディーでも会社によって違う名前で売っているケースもある。
鼻水がたらたら流れるような風邪によく効くNatrum muriaticumというレメディー。岩塩なのですが、日本語のガイドブックだと、ネイチュ・ミュアとかナト・ムールと書いてあるのがほとんどで、まぁそれは頭に入っている。でも、ドイツのレメディー大手のDHU(ドイツ・ホメオパシー・ユニオン)ではこの名前で売っていなくて、Natrum chloratum という名前で出している。アンドルー・ロッキーさんのホメオパシー大百科事典によると、ネイチュ・ミュアの方が別名らしいけど。まぁいいや。
で、薬局でこの綴りで注文しようとしても「ないですねぇ」という事になってしまって、DHUのホームページ でみてやっとこの事実に気がついた。こんな事が前にありました。
今回は、健登のPolypen、アデノイド肥大という事で良いかと思いますが、これの治療に使えるレメディーを見つけて・・・というかいつもお世話になっているWecker医師の休暇中の代理の女医さんが教えてくれたんだけど・・・これを注文しようとしたら、これがまたこのケースで。
Teucrium, Teucrium scorodonia, Teucrium marum, Teucrium scordium.どれなんだー!?。そして、これらのほとんどは実はMarum verumという全然違う感じの名前で売っていると・・・。
・・・またこれを確認しようとしてWecker医師に電話しても、またつながるまで何時間か電話し続けたりする羽目になりそうだし、何とか自力でつきとめたいな。
この電話がつながりにくくて困るっての、ドイツのホメオパシー事情として、普通のことらしいですね。優秀なホメオパスだと、どこでも大体そうだって。電話で済むってのは、ひっくり返せば、電話がつながらなくちゃいけない、という事だから。これも不便を感じる点の一つです。ある意味でホメオパシーが普及している証拠でもあるんだろうけど。
うちの場合は、今お世話になっているWecker医師は約300km離れた、ヴュルツブルク近郊に住む人だから、電話でたいていのことは済ませるのが前提です。でも、つながらなくちゃしょうがないですからね。
さて、色々な情報ページを読んで、結局、marum verumであるらしいことがわかり、電話で注文しました。近所の薬局に電話して注文し、数時間後に取りに行くというこのパターン、なかなか気に入っています。そのときに、もう一つ切らしているレメディーも注文しました。これはAntimonium tartaricum日本語の本ではアンチモンとかアンチ・タルトとか書いてあったかな。気管支炎や、痰の絡む咳にとてもよく効く。
後で嫁さんに取りに行ってもらって、帰ってきた嫁さん曰く。「なんだか名前が違うレメディーだけど、同じものだから安心して使ってくれと言われたわよ」
えっ!?それはきちんと調べて、あれがMarum verumであることはしつこいくらい検証したんだぞ。薬局のおばさん、勝手に別のに変えちゃったら困るよー。似た名前で全然違うものがあるんだから!と思って、見てみると、ちゃんとmarum verumが来ている。「???」となってしまったのですが、もう一つを見てみたら、Antimonium tartaricum じゃなくて見たこともない名前のレメディーが来ている。Tartarus Stibiatusだと。なんだこっちのことか?
またまたアンドルー・ロッキーさんのホメオパシー大百科事典でみたらなるほど、その通り。アンチモンの方がまたしても別名。
しかし、惑わされるなぁ。びっくりしたし、今回は。いい加減に誰かこういうの、統一してくれませんかっ!!