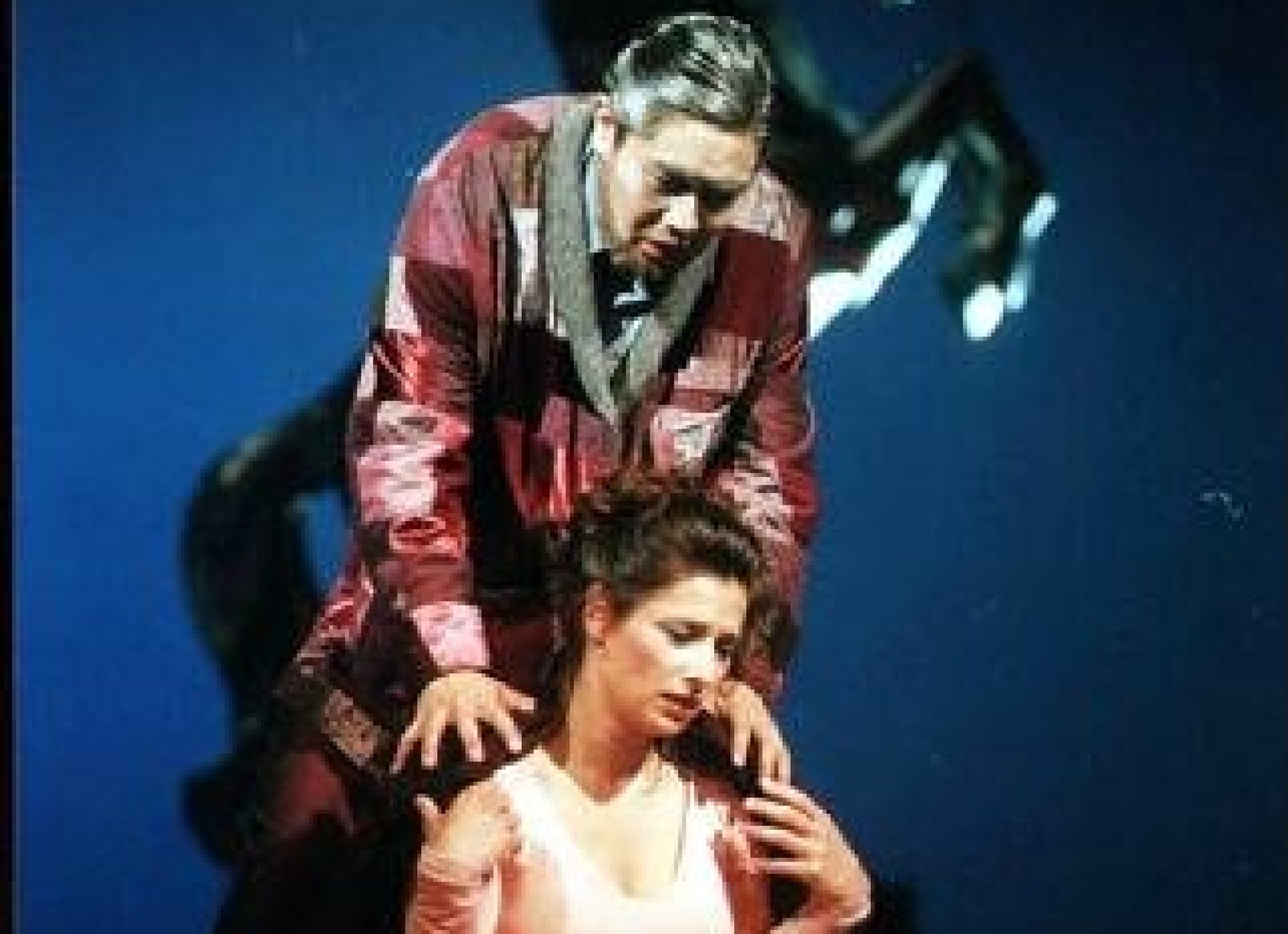昨日、今日とフォーレのレクイエム本番でした。
正確には、うちの劇場のオーケストラの今シーズン3回目のフィルハーモニーコンサートで、前半にラフマニノフの交響詩「死の島」(Die Toteninselとあるのですが「死者の島」かも)、ヨゼフ・ガブリエル・ラインベルガーという作曲家のオルガンコンチェルト、後半にフォーレのレクイエムというプログラムでした。
昨日も今日も客席は満員御礼。初日は録音のマイクがたくさん立っているし、僕らも歌う一を厳密に決められている関係で少し窮屈な感じがしましたが、今日はリラックスして演奏できました。とても良い演奏になったと思います。レクイ...
エムという曲の性格上、ブラボーなんかは出しにくいんじゃないかと思うんですが、お客さんの反応も熱狂的でした。フェルツ氏の指揮ぶりは練習よりさらに熱気を帯びて素晴らしかった。また合唱が非常に良く稽古されていて、演奏者全員が一体となった素晴らしい空間でした。
オーケストラに前にずっと座っていると、後ろから素晴らしい音楽の波でマッサージを受けているような肉体的な快感がありました。うまく言えないんですが、日本のオーケストラとドイツのオーケストラの違いがやはりあるなぁと思いました。うちのオーケストラは確かにこのクラスの劇場のオーケストラとしては規模が大きいし、ドイツのオーケストラのランクで言うとB+で、劇場のランクよりオケのランクがいい感じなんですが、そこはやはり田舎の劇場ですから、メトロポリタン東京でバリバリやっている在京オーケストラに比べるとレベルが上とはいえないと思うのです。でも何か、音を生み出すときに国民性が出るのか、なにか違うんですね。遠慮のなさとか、個人主義的なヨーロッパの雰囲気が音楽の質(善し悪しと言うより、キャラクターの違い)に影響を与えているように思います。良くわかっていない部分もあるので、まぁあまり無責任なことはいえないんですけど、そう感じます。フレーズ感かなぁ。
昨日、楽譜のカバーを用意しようと思って、久しぶりに黒い楽譜カバーを取り出したら、中に楽譜が入ったままになっていました。前に使ったときのものですが、ブラームスの四重唱のコピー楽譜で、表紙にもとの楽譜の持ち主の名前が入っていてはっとしました。その人は僕にとってドイツ歌曲の分野で、ベルリン時代の僕の恩師だった人です。
素晴らしい先生で、僕はリート解釈という範囲だけでなく、音楽とは何かというかなり根本的なものを彼女からもらったと思っています。ドイツ女性らしく骨太で存在感のある音楽づくりで、それまで僕が考えてきた音楽の捉え方を肯定し、さらに先に進めるチャンスを与えてくれました。彼女の方でも僕との作業をとても喜んでくれたし、僕のゲラでの契約の事もとても喜んでくれて、実家に帰るときに通るところだから、何か歌うときは聴きに行くから教えてくれと言っていたのです。
ところが彼女は僕が日本にいた去年、急速に進行した癌のせいで亡くなったのです。人間的にも音楽的にも大切な僕のかけがえのない一部を失ってしまった気持ちでした。
彼女の名前を偶然にもレクイエムの演奏の本番の日に目にして、昨日の演奏中は彼女のことばかりを考えていました。この偶然は、神様が僕に、このレクイエムの演奏を通じて彼女のことに思いを馳せ、彼女の冥福をもう一度祈ってしっかりと心に刻む機会を与えてくれたのかも知れないと思いました。
彼女のためにも明日もう一度アルテンブルクである本番をしっかり務めたいと思います。
2001年11月30日(金)スクリプトで読み込み