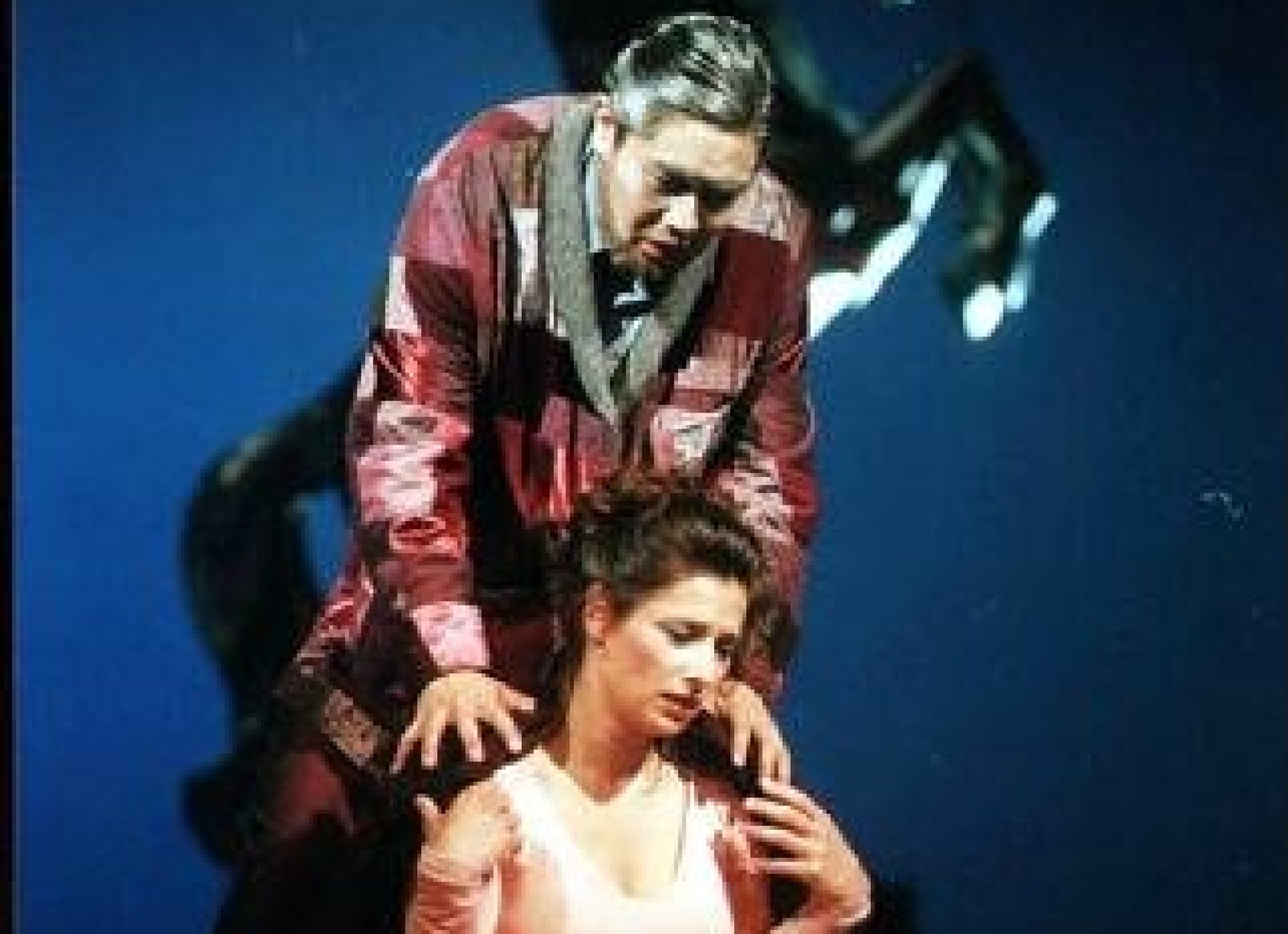昨日はプーランク「カルメル修道女の会話」の二回目の本番でした。日曜日午後の公演。この作品はプレミエの日記にも書いた通り、かなり内容がどぎついので、決してゲラのような平和な街向けの作品ではありません。で、インテンダントで演出もしたマティアス・オルダーグはこの二回目の公演の客入りがかなり気になっていたようです。結果としては、アボがほとんど入っていなかったにも関わらずかなりのお客さんが入って、まずは一安心でしょうか。
昨日はプーランク「カルメル修道女の会話」の二回目の本番でした。日曜日午後の公演。この作品はプレミエの日記にも書いた通り、かなり内容がどぎついので、決してゲラのような平和な街向けの作品ではありません。で、インテンダントで演出もしたマティアス・オルダーグはこの二回目の公演の客入りがかなり気になっていたようです。結果としては、アボがほとんど入っていなかったにも関わらずかなりのお客さんが入って、まずは一安心でしょうか。
ビーレフェルトでシュタイナー学校の教師をしているヴェルナー・ハースの事は前にも書きました。ビーレフェルトは今学校が秋休みで、それを利用してゲラの劇場の公演を見たいと前から彼は言っていて、10月5日のトスカを見てもらおうと思っていたんだけど、秋休みの後半はそのあとの授業の準備もしたいと言うことで、このカルメルを見に来ました。
 この写真に写っている冊子。これは、彼が台本・作曲・指揮・演出を一人でやってのけたミュージカル「Courage」の公演プログラムです。実際に起きた事件に彼は動かされてこの作品を作ったのですが、なんとその事件が起きた村でも公演をしてきたんですな、彼は。それが僕らのカルメルのプレミエと同じ日で、僕はもちろん見に行けなかったんだけど、その村での公演、ビーレフェルトでの公演、両方とも毎日売り切れで大成功を収めたようです。
この写真に写っている冊子。これは、彼が台本・作曲・指揮・演出を一人でやってのけたミュージカル「Courage」の公演プログラムです。実際に起きた事件に彼は動かされてこの作品を作ったのですが、なんとその事件が起きた村でも公演をしてきたんですな、彼は。それが僕らのカルメルのプレミエと同じ日で、僕はもちろん見に行けなかったんだけど、その村での公演、ビーレフェルトでの公演、両方とも毎日売り切れで大成功を収めたようです。
どんな事件が起きたかって言いますと・・・プログラムから抜き出して訳してみましょう。

2004年の二月のある夕方、ヴェトナム人家庭Le Daの家のドアをノックする者がいた。驚愕する隣人の目の前で、5人の家族全員が連行され、ヴェトナムに強制送還されてしまった。
両親は17年もドイツに住んでおり、旧東ドイツ時代に既にドイツに来ていた。3人の子供は皆ドイツで産まれ、東ハルツのテューリンゲンの小さな村ブライヒェローデが彼らの故郷であり、彼らの母国語はドイツ語であった。にもかかわらずこの家族は滞在許可の期限が過ぎた後は、ドイツへの不法滞在を「黙認」されていたに過ぎなかったのだ。
父親がいくつかの不法行為を置かしてしまった結果、法的にはこの強制送還を防ぐ方法は存在しなかった。それどころか、裁判所、役所、政治はどのレベルにおいても統一見解を持っていた。強制送還は正当な措置だったと言うわけである。
長男のDonは彼の先生に手紙を残すことに成功し、それによって彼らの居場所を公に知らせることが出来た。しばらく途方に暮れた後、隣人、同級生達、ブライヒェローデ村の住人達はとにかく住民運動「Rückkehr(帰還)」をはじめた。22ヶ月のあいだ、毎週火曜日に残された家の前での警告活動を阻止し、弁護士や政治家に働きかけ、役所にも出かけて、このスキャンダルが世間の関心を失わないように活動した。
しかし一番大切な目標は、子供たちをドイツに呼び戻すことだ。根気と粘り強さで次第に、政治や官庁から人間的な解決をひき出すことが出来てきた。多くの反発にもかかわらず結束は固くなり、次から次へと増大する、計り知れぬ人間的な、そして経済的な負担を埋めることが出来るようになって行った。
2005年のクリスマスの少し前に、Le Da夫人と子供達は、そうこうしているあいだにきれいに改装された家に戻ってきた・・・。
すごい話ですよ。ブライヒェローデでの公演では、もう泣いちゃう人が続出だったようです。ヴェルナーはうちの劇場にも公演しないか、と持ちかけるつもりがあるようで、僕も一役買うかな。
そういえば、ヴェルナーは僕の声を生で初めて聴いたわけで、しかも前に聴かせたのは歌曲だったから、かなりイメージが違ったようで、「また君のために曲を書きたくなってきた」といってました。でも前に僕に献呈してくれた3曲のうち、3曲目はまだ歌ってないんですよね。どこで初演しようか?